皆様、こんにちは。
我が家にはマレーシアに関わる書籍がたくさんあり、日本人の友人からは「マレーシア図書館」と言われたり、マレーシア人からは「大学のマレーシア研究室みたい」とか言われたりするほどです。
そんなマレーシア図書館からご紹介したい本はたくさんあるのですが、今回取り上げるのはこちら。個人的な感想を中心にご紹介します。
- 【詩人・金子光晴の旅の軌跡を写真と詩でめぐる】
- 【風変りでたくましい詩人金子光晴】
- 【相性抜群!金子光晴のダメっぷりと東南アジアの空気感】
- 【金子光晴が長期滞在した小さな町バトゥ パハッ】
- 【何者でもない自分を受け容れてくれる、何もない町】
- 【最後に】
【詩人・金子光晴の旅の軌跡を写真と詩でめぐる】
今回ご紹介する一冊は、『金子光晴の旅 かへらないことが最善だよ。』。
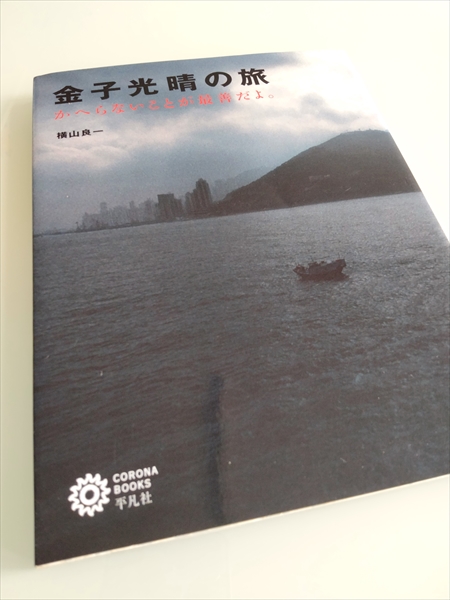
『金子光晴の旅 かへらないことが最善だよ。』金子光晴 著/横山良一 写真/平凡社
金子光晴は1928年から1932年までの五年間、世界放浪で渡り歩いたアジア、ヨーロッパ各地でいくつもの詩を残しています。その軌跡を写真家である横山良一さんが辿り、写真、そして金子光晴が執筆した原文のままに紹介している一冊です。
【風変りでたくましい詩人金子光晴】
金子光晴…。バックパッカーの元祖なんて呼ぶ人もいます。それも確かにそうかもしれませんがそれ以前に、1930年頃の時代にこれだけの旅をしてるのですから、実際結構な変人だと私は感じます(笑)。
私が金子光晴を知った当初は、彼がマレーシアでもずいぶんとマイナーな場所であると言えるJohor州(ジョホール州)の海辺の町Batu Pahat(バトゥ パハッ)を訪れていたことにとても興味を抱きました。そんな好奇心から彼の著書を読み漁ったのですが、読めば読むうちに「この人本当にダメな男だな」と思うようになりました(笑)。
放浪記として挙げられる、『どくろ杯』『ねむれ巴里』『西ひがし』。そして、マレーシア好きにはぜひとも読んでいただきたい、彼の代表作『マレー蘭印紀行』。
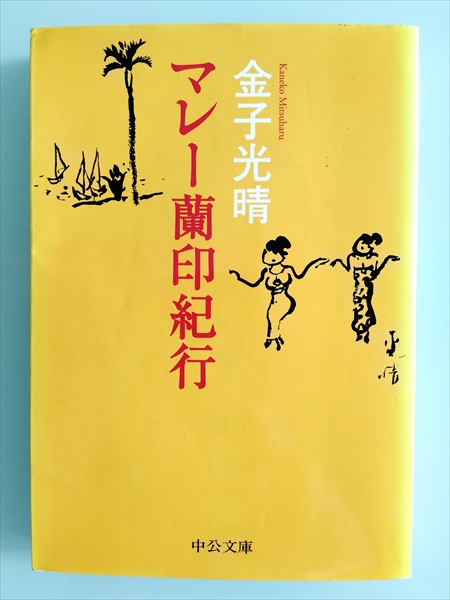
どの本も旅行記として読めば本当に面白いです。しかも、現代ではなく大正から昭和という時代にそれをやってのけた金子光晴は相当変わり者で、その彼の視点からのマレーシアの風景を読むこともとても楽しいです。
【相性抜群!金子光晴のダメっぷりと東南アジアの空気感】
ただ、「旅行記」として読んでいる分には面白くはあるものの、この金子光晴という人物を著書を通して見てみると、本当にダメな男というに尽きるかと。そして、そのダメっぷりが妙に東南アジアのまとわりつく空気に馴染んでしまっていると感じます。
お金がないのに放浪して女に手を出してみたり、一方で男としてのプライドは捨てきれない感がある。どの角度からひいき目に見てもダメじゃない要素を見つけるのが難しい、ダメ男です。お金がないなら放浪などせず日本に帰ればいいし、堅実に職に就いて稼ぎを貯めればいい。奥さんとのことも、彼女のこれからの人生の幸せのために男らしく自由にしてあげればいい。
と、理屈ではそう思うけれど、それができないのがきっと人間ですね。私自身がいつもつらいことから逃げる傾向にある性格なので、そういう人間の弱さが見える感じも嫌いではないのです。人間てそんなものでしょう?と思うから。
金子光晴の作品、そしてその当時の風景を映し出すこの横山良一さんの本にどうして私がそんなに惹かれるかと言うと、きっとこのダメな男を容易に受け容れて包み込んでいるとも思える、まとわりつく空気感が写真や文章から感じることができるからなのかも、とふと思ったのでした。
【金子光晴が長期滞在した小さな町バトゥ パハッ】
金子光晴がその土地を気に入り長く滞在した、マレーシアの小さな町バトゥ パハッ。何度訪れてもこの町は特に何もなく、何もないどころかきっと若者は退屈すぎて都会に出て行ってしまうだろうな、と思うほど閑散とした町です。

金子光晴が旅した当時、日本人倶楽部があった建物。今は特にこれといった人が集まる場所ではなく、一階に小さなお店が営まれている程度です。

【何者でもない自分を受け容れてくれる、何もない町】
何もないこのバトゥ パハッで金子光晴は何をするでもなく過ごしますが、その「何もしない」日々のなかで自分が自分らしいままにいられるのはここだ、と思っている様子がうかがえます。
世界のたくさんの地を訪れ、その中には刺激をたくさん受けられるパリや上海などの大都市もあったのに。どこに行っても居場所、身の置き場所の実感が得られない「何者でもない」金子光晴。でも、そんな彼をなんの屈託もなく受け容れたのはマレーシアの小さな町、というのが私は読んでいてとてもぐっとくる部分でした。
私自身、人があまり興味を示さないような町や場所に惹かれるところがあり、マレーシアをずっと旅し続けていた頃もよく、日本人はもちろんマレーシアの人達からも「そんなところに何をしに行くの?」と聞かれることが多かったのです。
私にとっては、周りの皆が楽しいと思うような都会や見どころ満載の観光地よりも、何もなくてただ歩いている、ただ見つめていることができる町に身を置くことがとても落ち着く時間でした。
多分それは、私が何か大きなことができる人間でもなく、そんな取り柄も少ない自分でも居心地の悪さを感じずに自然体でいられる場所が好きなのかなと自己分析しています。
そんな私は、当時このバトゥ パハッに長く身を寄せた彼の気持ちが分かるような気がしながら金子光晴の作品を読んでいたのでした。
【最後に】
なぜこの金子光晴という人物、そしてその軌跡を辿ったこの一冊にどうして惹かれたのかを記してみました。
どうひいき目に見てもダメ男である金子光晴本人には男性としては全く惹かれないのだけれど、それでもこの金子光晴の世界感に惹かれた人が日本には少数派ながら存在していて、私も実はその一人であることは確か。
そして、金子光晴という糸をたどってマレーシアにたどり着くという地図が面白いなとも感じていて、そういう意味では金子光晴って偉大!と思ってしまいますが、実際は奥さんは本当に大変だったと思うので、私はこういう人と夫婦にはなりたくないですけど(笑)。(どんな締めなの)